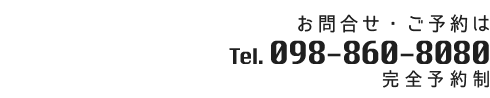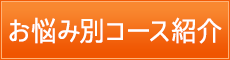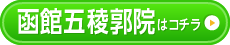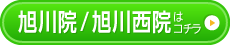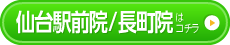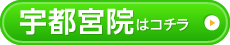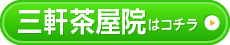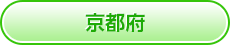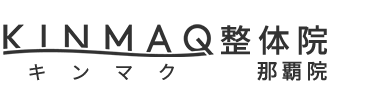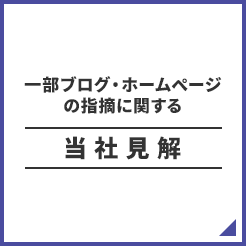肩こりからくる頭痛に悩んでおり、肩甲骨周りのアプローチによって、肩こりと頭痛を解消したいと考えている人も多いのではないでしょうか?肩こりからくる頭痛の主な原因は緊張型頭痛といわれ、これに対しては肩甲骨へのアプローチを行うことが非常におすすめです。
今回は、肩こりによる頭痛の原因、緊張型頭痛の概要、肩甲骨の重要性、対処法と予防法について解説します。肩こりからくる頭痛で悩んでいる方は、この記事をぜひチェックしてみてください。
肩こりが原因で頭痛になる?
 肩こりが原因で頭痛になる理由と原因について解説します。肩こりからくる頭痛で悩んでいる方は、先ずは原因について理解し、対処法と予防法を学びましょう。
肩こりが原因で頭痛になる理由と原因について解説します。肩こりからくる頭痛で悩んでいる方は、先ずは原因について理解し、対処法と予防法を学びましょう。
肩こりによる頭痛の原因は緊張型頭痛
肩こり由来の頭痛の主な原因は偏頭痛ではなく、緊張型頭痛といわれています。緊張型頭痛とは、圧迫感や締めつけ感が主体の頭痛で、頚部痛、肩こり、めまい、光や音の過敏などの不調や症状が誘発されます。
しかし、五十肩などの肩関節の炎症や頚部疾患などの病気を患っている危険性もあり、上記の症状に加えて腕~手のひらのしびれ、筋力低下など、症状の悪化が危惧されるケースでは、医療機関を受診して医師の診断と治療を受けるように心掛けましょう。
肩こりで緊張型頭痛が起きる原因
緊張型頭痛の発生メカニズムは明確に解明されていませんが、慢性的なストレスや首から肩にかけての筋肉の緊張と血流不良によって、症状が引き起こされると考えられています。また、頭蓋骨を覆う筋膜の感受性が増大し、痛みを感じる神経が刺激されます。
デスクワークや生活習慣などの長時間の同じ姿勢や、力作業を続けていると頭から首、背中にかけての筋肉に疲労物質が蓄積されます。このように過度な緊張が継続すると、血流不良を生じることで肩こりが発生し、この肩こりが要因となって緊張型頭痛が引き起こされます。
緊張型頭痛には肩甲骨へのアプローチが重要
 緊張型頭痛には肩甲骨へのアプローチを行うことが非常に重要で、肩こり対策の鍵は肩甲骨の機能が重要なポイントとなります。以下に肩甲骨へのアプローチの重要性と、肩こりを楽にする肩甲骨ストレッチについて解説しますので、肩こり由来の頭痛で悩んでいる方はぜひ試してみてください。
緊張型頭痛には肩甲骨へのアプローチを行うことが非常に重要で、肩こり対策の鍵は肩甲骨の機能が重要なポイントとなります。以下に肩甲骨へのアプローチの重要性と、肩こりを楽にする肩甲骨ストレッチについて解説しますので、肩こり由来の頭痛で悩んでいる方はぜひ試してみてください。
肩こり対策の鍵は肩甲骨が握る
肩こり対策の鍵は肩甲骨が握っており、主に肩甲骨に付着した筋肉の影響を受けます。肩こりの原因となる筋肉は首から肩甲骨に存在します。肩甲骨は背中部分の肋骨上にあり、肋骨の上でさまざまな方向に可動します。
長時間うつむいた猫背姿勢を続けていると、両側の肩甲骨が外側に広がって固定されてしまいます。このような状態になると、肩甲骨に付着した筋肉の血行不良を生じ、筋肉の伸張性が失われ肩甲骨や鎖骨の可動性が低下します。
特に肩甲骨に付着する「肩甲挙筋」と「菱形筋」が肩こりと深く関係しますが、これらの筋肉は深部に存在するため、マッサージではほぐしにくい筋肉です。
肩こりを楽にする肩甲骨ストレッチの方法
肩甲骨を可動させることで「肩甲挙筋」や「菱形筋」といった、肩甲骨周囲筋へのストレッチを行い、肩こりを解消する効果が期待できます。肋骨上にある肩甲骨をはがすようなイメージで可動させ、肩甲骨に付着した周囲の筋肉をほぐします。
以下に、タオルを用いた肩甲骨ストレッチの方法をご紹介しますので、肩こり・首こり、頭痛などで悩んでいる方はぜひ試してみてください。
|
【肩甲骨のタオルストレッチ】
|
整体院の施術を受ける選択肢もある
慢性的な肩こりや違和感、緊張型頭痛で悩んでいる場合や、いくつかの対処法を試しても症状が継続している場合は、整体院で頚から肩甲骨、背中、腕にかけての筋膜ケアの施術を受けることで、筋肉の緊張状態が楽になる可能性があります。
肩こりからくる頭痛で悩んでいる方は、筋膜リリースなどのアプローチを得意とする整体院にご相談の上、肩まわりの筋膜を整えるとともに筋肉をほぐしてみてください。
肩こりからくる頭痛を予防するコツ
 肩こりからくる頭痛を予防するコツについてポイントを解説します。日々の生活習慣を見直して、肩こりや頭痛の原因となる筋肉の緊張状態を解消しましょう。
肩こりからくる頭痛を予防するコツについてポイントを解説します。日々の生活習慣を見直して、肩こりや頭痛の原因となる筋肉の緊張状態を解消しましょう。
同じ姿勢で長時間過ごさない
同じ姿勢で長時間過ごすと筋肉が硬くなり、こりや張りを生じて肩こりや頭痛、腰痛を誘発します。同じ姿勢で作業を続ける際には、間に休憩時間を設けて適度に関節を動かし、筋肉が固まらないようにケアをしましょう。
正しい姿勢を身に付ける
立っている姿勢と座っている姿勢に関係なく、みぞおちを少し持ち上げて顎を引き、骨盤上で上半身と頭部が一直線となる姿勢を意識するように心掛けましょう。
特にスマートフォンやタブレットなどを見る際には、猫背姿勢とならないように注意してください。スマートフォンなどを使用する際には、前述した良い姿勢を保持した状態で、目の高さに位置するように注意しましょう。
体に合う枕を使う
顎、首、肩の力が抜けてリラックスでき、左右に寝返りしやすい枕を使用するように心掛けましょう。枕が高すぎる場合や、逆に低すぎてしまうと首の負担や呼吸のしにくさを招いてしまい、肩こりに関連した筋肉を緊張させる危険性があるため注意してください。
運動をする習慣を付ける
肩や肩甲骨を可動させる運動を行うことをおすすめします。これらの運動を行うことで、筋肉内の血行不良が改善され、肩こりや頭痛を軽減させる効果が期待できます。
肩回りを可動させる動的なストレッチや筋力トレーニングだけでなく、適度に腕を振るウォーキングやジョギング、ラジオ体操、水泳などもおすすめの運動です。
肩こりからくる頭痛に悩んでいる方は肩甲骨へのアプローチを
 今回は、肩こりからくる頭痛に悩んでいる方に向けて、原因や緊張型頭痛の概要、肩甲骨の重要性、対処法と予防法について解説しました。肩こりからくる頭痛の多くの原因は、緊張型頭痛が関連しており、肩甲骨へのアプローチや「肩甲挙筋」と「菱形筋」のストレッチを行うことが非常に重要です。
今回は、肩こりからくる頭痛に悩んでいる方に向けて、原因や緊張型頭痛の概要、肩甲骨の重要性、対処法と予防法について解説しました。肩こりからくる頭痛の多くの原因は、緊張型頭痛が関連しており、肩甲骨へのアプローチや「肩甲挙筋」と「菱形筋」のストレッチを行うことが非常に重要です。
さまざまな対処法を試しても症状が軽減しない方は、筋膜ケアの施術を受けることで肩まわりの緊張状態が楽になる可能性があります。
肩こりからくる頭痛に悩んでいる方や、肩甲骨のアプローチ方法が分からない方は、ぜひ整体院にご相談の上、ご自身に合ったセルフケアを試してみてください。